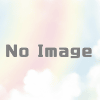ペットが亡くなってから感情が動かない…「麻痺」した心へのアプローチ
「涙も出ない」「何をしても心が動かない」「悲しいとも感じられない」——
大切なペットを亡くしたのに、自分の心が“無”になってしまったように感じることはありませんか?
悲しみすら感じられない自分に、「おかしいのでは?」と不安になる方も多いでしょう。
ですが、これは「感情の麻痺」と呼ばれる、ごく自然な心理的反応のひとつです。
この記事では、感情が動かない理由と、その“止まった心”を少しずつほぐしていくためのアプローチをご紹介します。
感情が麻痺するのは「心の防衛反応」
人は、あまりにも強いショックや悲しみを受けると、心がそれに耐えられなくなります。
その結果、無意識のうちに「感じることを止める」ことで心を守ろうとするのです。
この状態を、心理学では「解離(かいり)」や「感情の麻痺」と呼びます。
感情麻痺に見られる主な特徴:
- 悲しみや怒りが湧かず、空っぽのような感覚
- 周囲の出来事に関心が持てない
- 無感情のまま時間だけが過ぎていく
- 涙も出ず、「自分は冷たい人間なのでは」と思ってしまう
これらの反応は、あなたの心が限界まで頑張った結果として起きているものであり、異常ではありません。
感情の麻痺をほぐすためのアプローチ
1. 「無感情な自分」を否定しない
まずは、感じられない自分を責めないことが大切です。
「今は感じられないだけ」「心が休もうとしているんだ」と、受け止めるところから癒しが始まります。
2. 「感じる」ではなく「気づく」から始める
感情を動かそうとするのではなく、まずは
- 今日は空がきれいだと気づいた
- この音楽は心地よいかも
- コーヒーの香りを久しぶりに意識した
といった、五感の“気づき”に目を向けてみましょう。
これは、心の再起動ボタンのようなものです。
3. 写真や思い出にふれてみる
最初は何も感じなくても、何度か見たり触れたりするうちに、少しずつ感情がにじんできます。
焦らず、「心にさざ波が立つ瞬間」を見逃さないことが大切です。
4. 小さな行動から始める
感情が動かなくても、行動を先に起こすことで心が後からついてくることがあります。
たとえば:
- 好きだった場所へ散歩に行く
- あの子の好きだったおやつを供える
- 手紙を書いてみる(感情がなくてもOK)
行動は、止まった心を少しずつ動かすスイッチです。
5. 専門家のサポートを受ける
無感情の状態が長期間続くと、うつ病や解離性障害などのリスクが高まることもあります。
心療内科やカウンセラーに相談することで、心のブレーキをやさしく解除する手助けが得られます。
まとめ
ペットロスで感情が動かなくなるのは、あなたの心が「壊れないように」守っている状態です。
無理に感じようとせず、
- 「感じない自分」を受け入れる
- 五感で世界を少しずつ感じ取る
- 小さな行動で心に呼びかける
そんな穏やかなアプローチが、止まった時間を動かし始めるきっかけになります。
心は必ず、再び動き出します。あなたのペースで、ゆっくりと。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
ペットロスで揺れる感情とその向き合い方:怒り・罪悪感・否認・孤独